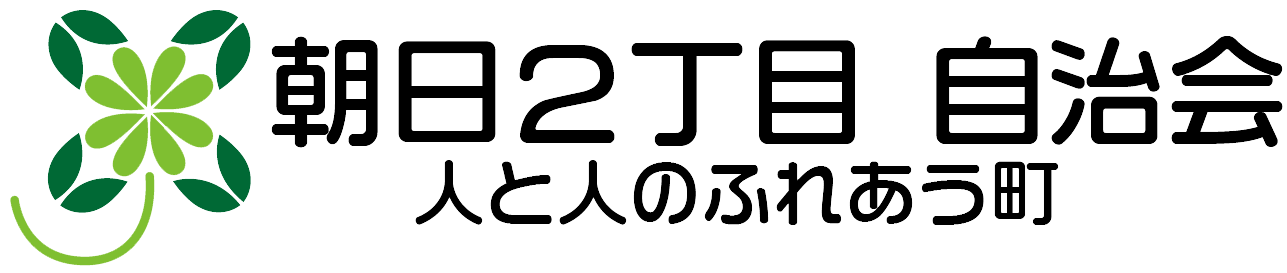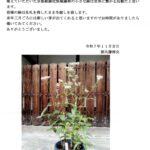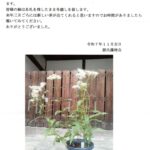当ホームページで「10月11日。京都革堂行願寺・下御霊神社・寺町商店街で開催されている『令和7年度藤袴祭』(画像01)に行ってきました。」の記事で、メイン会場の革堂行願寺には、今年7月6日に開催された『藤袴植え付け体験会』で鉢植えしたフジバカマが無事花を付けていました(※02・03)…(後略)」とご案内していましたが…
体験会を主催した事務局から、藤袴の匂い袋と入浴剤などが届きました。(04:以下同封の礼状兼案内文より)
7月6日には革堂(こうどう)さんにて体験会にご参加いただきありがとうございました。
今年の近畿地方は異例の早い梅雨明けとなり、暑さの中での植え付け体験となりました。
その後も、猛暑が続き、源氏藤袴会さんでは、日々の水やりに加え、日よけ(覆い)の設置、大型扇風機の使用、さらには藤袴の大敵であるバッタの大量発生による鉢の移動などにご尽力いただきました。
お陰で、10月初旬には、皆様の鉢の藤袴は美しく、そして芳しく開花いたしました(05・06)。10月10日~13日の期間、開催された藤袴祭では、多くの人と蝶たちが集まり(07~12)、咲き誇る藤袴を楽しむ姿が見られました。
さて、このたび、藤袴の刈り取りと乾燥が完了しましたので、藤袴にちなんだオリジナル陶器(13)絵葉書(14)とともに送付させていただきます。
藤袴は乾燥するとより香り立ちます。平安貴族は、とりわけこの香りを愛で、匂い袋に入れたり、入浴剤や洗髪に使用されたといいます。平安末期に編纂された日本最古の香りの指南書『薫集類抄』には、浴湯香には、澤蘭(藤袴)を加えよと記されています。
皆様も、王朝時代に思いを馳せて、同封の小さなオーガンジー袋(写真15下)は、匂袋としてタンスなどに入れてお使いください。
また、大きいオーガンジー袋(15上)は、お風呂に入れてみてください。お風呂に入れる場合は、事前に別の容器で熱めのお湯に浸してから湯船にいれるとよく香ります。ただ、入浴後、藤袴のお湯をそのままにしておくと湯槽に色が付く可能性があるため、早めにお湯を抜いて浴槽を洗ってください。(後略)
また、皆様の鉢は名札を残したまま冬越しをいたします(16・17)。
来年の三月ごろには新しい芽が出てくると思いますのでお時間がありましたら覗いてみてください。
 ※写真・画像の一部は、当ホームページ「令和7年度藤袴祭」&「特別展世界遺産縄文」&アサギマダラ号外(2025年10月14日付け)で使用したものを再使用しています。
※写真・画像の一部は、当ホームページ「令和7年度藤袴祭」&「特別展世界遺産縄文」&アサギマダラ号外(2025年10月14日付け)で使用したものを再使用しています。
皆様も、フジバカマを乾燥させて、匂い袋、入浴剤作りにチャレンジしてみては如何でしょうか。
また、当記事の要約版をpdfにして添付いたしました。(発起人代表:井上)
 ※写真・画像の一部は、当ホームページ「令和7年度藤袴祭」&「
※写真・画像の一部は、当ホームページ「令和7年度藤袴祭」&「